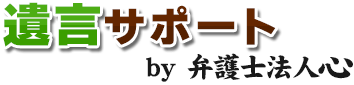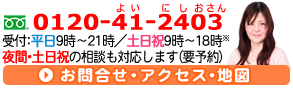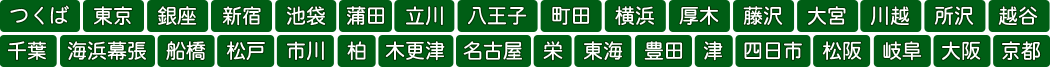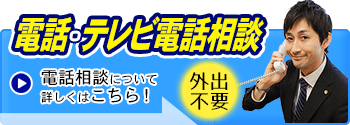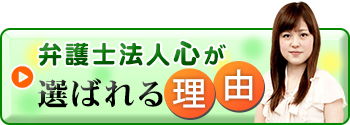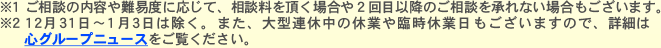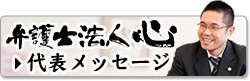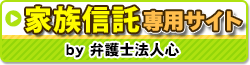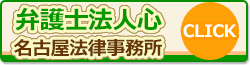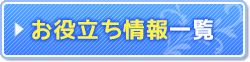遺言作成の流れ
1 まずは遺言に詳しい弁護士を探しましょう
ご自身で遺言書を作ることも可能ではありますが、詳しい知識がない中で行うのはリスクも伴いますので、弁護士に依頼するのが安心かと思います。
遺言に詳しい弁護士を探す際のポイントは、「相続税に詳しいか」「遺言の裁判に詳しいか」にあります。
相続税は特例の適用によって、税額が大幅に異なります。
相続人の最終的な手取り額が変わることになりますので、税金まで考慮して遺言を作ってくれる専門家が適切です。
また、遺言では、例えば、仮に長男が自分よりも先に亡くなっていた場合に備えた予備的遺言がなかったために、遺言無効の裁判になってしまった、といったことがよくあります。
このような裁判実務に関する動向は弁護士しか分かりません。
したがって、相続税・遺言の裁判の両方に詳しい弁護士がおすすめです。
2 自筆にするか公正証書にするか決める
相続に関する法改正以前は、自筆の遺言書の場合は保管してくれる公的機関がないという点で、公正証書遺言の方がおすすめでした。
ただ、現在では、法務局で自筆の遺言書を保管してくれるサービスが始まりましたので、保管の有無ではあまり違いはありません。
自筆の場合は、自分で手書きしなければならない点や保管してくれる法務局まで本人が行かなければならない点などの煩わしさはありますが、すぐに何度でも書き直すことができるというメリットもあります。
公正証書の場合は、公正証書で書き直すためには再度公証役場に行かなければならない面倒さや、概ね5~10万円程度の公証人費用がかかる点はありますが、出張費を支払えば公証人が自宅や施設等にまで来て作成し、保管も受けてくれる点がメリットです。
3 文案を弁護士と作成する
ご自身の遺産の分け方に関する希望を弁護士に伝えます。
この際、大事なことは、希望どおりの遺言書を作った場合、その内容に税金面や裁判面でリスクになることはないかといった懸念事項を質問し、弁護士側から提案をもらうことです。
その上で、文案を作成しましょう。
4 文案を遺言書にする
自筆証書遺言の場合は、ご自身で手書きをします。
書き方には様々なルールがありますので、それを確認した上で作成する必要があります。
公正証書遺言の場合は、公証役場で予約を取り、作成してもらいます。